
今回は2018年3月発売の新しい作用機序を持つ、抗インフルエンザウイルス剤の新薬であるゾフルーザ錠(バロキサビル マルボキシル)の服薬指導をまとめました。
なお、現時点では予防の効能はありません。
ゾフルーザの特徴
ゾフルーザの特徴は下記の3点です。
1.単回経口投与
2.小児から成人まで使用可能だが、用量が従来の薬剤より複雑
3.新しい作用機序
1.単回経口投与
ゾフルーザはA型及びB型インフルエンザウイルス感染症患者に対して単回経口投与で有効性が期待できるため、イナビル同様に1回の使用で治療を完結できます。
2.小児から成人まで使用可能だが、用量が従来の薬剤より複雑
錠剤も小さく、小児から成人まで幅広く使用可能です。
ただし、従来の薬剤は用量設定が比較的シンプルですが、ゾフルーザは小児から成人まで4段階の用量設定となっているため用量が複雑です。
3.新しい作用機序
従来のタミフル、イナビルなどのノイラミニダーゼ阻害剤と作用機序が異なります。
ノイラミニダーゼ阻害剤は新しく形成されたウイルスの感染細胞からの遊離を阻害することにより、ウイルスの増殖を抑制します。
これに対して、ゾフルーザはインフルエンザウイルス特有の酵素であるキャップ依存性エンドヌクレアーゼの活性を選択的に阻害し,ウイルスの mRNA 合成を阻害することで、インフルエンザウイルスの増殖を抑制する新しい作用機序の薬剤となります。
ゾフルーザ(バロキサビル マルボキシル)の概要
服薬指導難度
効能
A 型又は B 型インフルエンザウイルス感染症
包装・規格
他の抗インフルエンザウイルス剤と異なり、1回分の包装はないため薬局としてはあまり嬉しくない包装かと思います。
・ゾフルーザ錠 10mg:PTP10 錠(10 錠 ×1)
・ゾフルーザ錠 20mg:PTP10 錠(10 錠 ×1)
用法・用量
1.通常,成人及び 12 歳以上の小児には,20mg錠2錠を単回経口投与する。
ただし,体重 80kg 以上の患者には20mg 錠4錠を単回経口投与する。
2.通常,12歳未満の小児には,以下の用量を単回経口投与する。
・40kg以上の場合:20mg錠2錠
・20kg以上40kg未満の場合:20mg 錠 1 錠
・10kg以上20kg未満の場合:10mg 錠 1 錠
食事の影響
空腹時投与と比べ、食後投与でAUCが36%減少しますが、臨床上の問題はないようで、用法に食事の規定はありません。
腎機能障害時の投与量
製薬会社に確認したところ、腎機能障害時のAUCなどを検証しているわけではないが、ゾフルーザは腎排泄の寄与は小さく,主に胆汁を介した糞中排泄によるものと考えられており、腎機能低下例でも減量の必要はないとのことでした。
タミフルは腎機能低下により減量が必要であるため、腎機能低下例ではゾフルーザを使用するという選択肢ができました。
特に腎機能低下してるが、クレアチニン値がわからず、かつイナビルなどの吸入もテスター吸ってもらった感じ、吸えそうもない場合(高齢者など)では良い代替薬となるかと思います。
名前の由来
XO(ノックアウト,~がない)+ influenza からXofluza(ゾフルーザ)と名付けられています。
異常行動の指導せん
下記の3種類の指導せんが存在します。
どれも製薬会社のホームページからも印刷可能です。
1.ゾフルーザ錠を処方された患者さんへ
2.ゾフルーザ錠を処方された患者さんとその保護者の方へ
3.ゾフルーザ錠を処方された患者さんの保護者の方に知っていただきたいこと
有用なのは3の指導せんで、「異常行動に対する具体的な対策」が記載されているので、取り寄せておくとよいかと思います。
1と2は体重と用量のわかりやすい図表となっているので、監査用として印刷しておいてもいいかもしれませんが、患者に渡す用途としての有用性は少ないかと思います。
1.ゾフルーザ錠を処方された患者さんへ
「成人」の体重と用量のわかりやすい図表となっています。そもそも成人用量は2段階でそんなに複雑ではないので必要性は少ないかと思います。
2.ゾフルーザ錠を処方された患者さんとその保護者の方へ
「小児」の体重と用量のわかりやすい図表の記載があり、監査用としてはわかりやすいかと思います。
患者に渡す用途としては下記の理由で誤解を与えがちなため注意が必要です。
不適切な記載
この指導せんのなかの記載項目に「ゾフルーザ錠と組み合わせてもよい飲み物や食べ物」があります。
この項目ではオレンジジュース、りんごジュース、ぶどうジュース、服薬補助ゼリー、アイスクリーム、ヨーグルト、プリンが紹介されています。
これを見ると錠剤をつぶしたり、溶かしてこれらに混ぜて飲ませてよいような印象をうけますが、製薬会社に確認したところこれはつぶしたりせずに飲食物を使い、錠剤のまま飲み込むという服薬補助ゼリーと同じ意味合いで食品も記載しているとのことでした。
3.ゾフルーザ錠を処方された患者さんの保護者の方に知っていただきたいこと
説明が必要な項目である「異常行動による転落等の事故に対する防止対策」について記載されてきるので取り寄せておいたほうがよい指導せんです。
従来では異常行動は小児・未成年者についての説明事項となっていましたが、2018.8月の改訂により「小児・未成年者」というくくりが削除されたため、すべての年齢に対して説明が必要となりました。
そのため、今後はすべての年齢にこの指導せんを渡して説明するのがよいかと思います。
ただし、この指導せんのタイトル部分などはまだ「保護者の方」という未成年用と誤解を与える記載となっているので、今後の指導せんの改訂が期待されます(2019.11現在ではまだ改訂されていないようです)。
出血(血便,鼻出血,血尿等について)の指導せん(2019.3月改訂に伴う追記)
2019.3月の添付文書改訂で「重要な基本的注意」に出血に関する内容が追記となり、服薬指導の際に出血の説明が必要となりました。
これに伴い製薬会社により出血(血便,鼻出血,血尿等について)の指導せんが新たに作成されました。
出血の説明は薬剤師にとって説明しにくい内容となるため、指導せんが役に立つため取り寄せておくことをお勧めします。
ゾフルーザの位置付け2019.11追記
2019年10月時点でのゾフルーザの位置付けが、日本小児科学会の「2019/2020 シーズンのインフルエンザ治療指針」に記載されています。
指針では、ゾフルーザが「小児における使用経験の報告が乏しいこと」及び「治療中に耐性ウイルスが出現すること」から「12歳未満の小児に対する積極的な投与を推奨しない」と記載されています。
また、「免疫不全患者では耐性ウイルスの排泄が遷延する可能性があり同薬を単剤で使用すべきではないと考える」との記載もされています。
<参考>
「2018/2019 シーズンのインフルエンザ治療指針」について
また、日本感染症学会でも、下記の提言がされています。
(1)12-19歳および成人:臨床データが乏しい中で、現時点では、推奨/非推奨は決められない
(2)12歳未満の小児:低感受性株の出現頻度が高いことを考慮し、慎重に投与を検討する。
(3)免疫不全患者や重症患者では、単独での積極的な投与は推奨しない。
どちらの学会も「免疫不全患者」では推奨しないようなので、該当患者にゾフルーザが処方された場合は念のため疑義照会したほうがよいかもしれません(ただし、免疫不全患者や重症者にこそ使用すべきであるという意見もあるようです)
<参考>
日本感染症学会提言「~抗インフルエンザ薬の使用について~」
ゾフルーザの服薬指導で確認すること
①年齢・体重の確認【用法・用量】
用量設定が複雑なので、年齢・体重を聴取し用量が適正か確認する必要があります。
比較的見落としがちな事例として下記のケースが想定されます。該当する場合は疑義照会対象となります。
・体重 80kg 以上にもかかわらず、通常の成人量20mg 錠 2 錠で処方されてしまう。(80kg 以上の場合は倍量の20mg 錠 4 錠になる)
・12歳以上にもかかわらず体重40kg未満だからと20mg 錠 1 錠で処方されてしまう。(12歳以上であれば成人量となる)
ゾフルーザの服薬指導で伝えること
①異常行動及び転落等の防止対策の説明【重要な基本的注意】
従来は異常行動は小児・未成年者についての説明事項となっていましたが、2018.8月の改訂により「小児・未成年者」というくくりが削除されたため、すべての年齢に対して説明が必要となりました。
前述した指導せんを用いて説明するのがよいかと思います。
抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無又は種類にかかわらず,インフルエンザ罹患時には,異常行動を発現した例が報告されている。
異常行動による転落等の万が一の事故を防止するための予防的な対応として,
①異常行動の発現のおそれがあること,
②自宅において療養を行う場合,少なくとも発熱から 2 日間,保護者等は転落等の事故に対する防止対策を講じること,
について患者・家族に対し説明を行うこと。なお,転落等の事故に至るおそれのある重度の異常行動については,就学以降の小児・未成年者の男性で報告が多いこと,発熱から 2 日間以内に発現することが多いこと,が知られている。
②すぐに服用することの説明【用法・用量に関連する使用上の注意】
すぐに服用したほうがよいことを説明します。
本剤の投与は,症状発現後,可能な限り速やかに開始することが望ましい。[症状発現から48時間経過後に投与を開始した患者における有効性を裏付けるデータは得られていない。]
③出血(血便,鼻出血,血尿等)の説明【重要な基本的注意】2019.3月改訂に伴う追記
2019.3月の添付文書改訂で「重要な基本的注意」に出血に関する内容が追記となり、服薬指導の際に出血の説明が必要となりました。
指導せんを用いて説明するのがよいかと思います。
<重要な基本的注意>
出血があらわれることがあるので、患者及びその家族に以下を説明すること。1)血便、鼻出血、血尿等があらわれた場合には医師に連絡すること。
2)投与数日後にもあらわれることがあること。
服薬指導例
実際の説明としては、指導せんを見せながら、「初回服薬指導の薬剤や抗生剤でルーチンで行うアナフィラキシー症状の説明」に追加するように話すのが伝えやすいかと思います。
「万一、合わない場合、蕁麻疹がでるとか苦しくなるとか鼻血や便や尿に血が混じる場合はすぐ連絡し受診頂いてますが、一般的によく使われる薬ですので」

ゾフルーザの服薬指導薬歴例
S)インフルエンザ治療
O)50kg
A)指導せんをわたして異常行動、玄関や窓の施錠など具体的な対策説明。万一、発疹、呼吸困難、鼻血、血便、血尿など出る際は連絡しすぐ受診指示。
すぐ服用指示。
P)状態確認









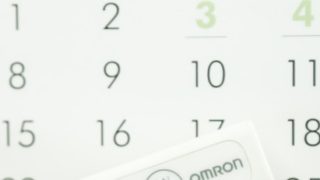


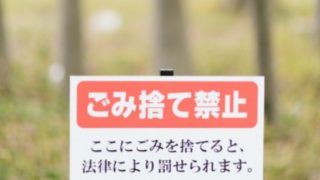







コメント