
2023年2月分のDSUのなかから薬局薬剤師に関係がありそうな薬剤を抜粋してまとめました。
今回はアムロジピンとニフェジピンの妊娠禁忌の削除が最も重要な内容かと思います。
①アセトアミノフェン【重大な副作用】
重大な副作用に「薬剤性過敏症症候群」が追加となりました。
<重大な副作用>
薬剤性過敏症症候群(頻度不明)
初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがある。
なお、ヒトヘルペスウイルス6(HHV-6)等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。
②アムロジピン【禁忌削除】
従来禁忌であった「妊婦又は妊娠している可能性のある女性」が削除となり治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与する旨の注意喚起に緩和されました。
<特定の背景を有する患者に関する注意>妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性に投与する場合には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
動物実験で妊娠末期に投与すると妊娠期間及び分娩時間が延長することが認められている。
③ニフェジピン【禁忌削除】
従来禁忌であった「妊婦(妊娠 20 週未満)又は妊娠している可能性のある婦人」が削除となり、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与する旨の注意喚起に緩和されました。
<特定の背景を有する患者に関する注意>妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある婦人に投与する場合には,治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること.動物実験において,催奇形性及び胎児毒性が報告されている.
投与に際しては,最新の関連ガイドライン等を参照しつつ,急激かつ過度の血圧低下とならないよう,長時間作用型製剤の使用を基本とし,剤形毎の特徴を十分理解した上で投与すること.
また,母体や胎児及び新生児の状態を十分に観察し,過度の血圧低下や胎児胎盤循環の低下等の異常が認められた場合には適切な処置を行うこと.妊婦への投与例において,過度の血圧低下等が報告されている.
④クロピドグレル【重大な副作用】
重大な副作用に「インスリン自己免疫症候群」が追加となりました。
インスリン自己免疫症候群(頻度不明)
重度の低血糖を引き起こすことがある。
⑤ビスホスホネート製剤【特定の背景を有する患者に関する注意】
「特定の背景を有する患者に関する注意」の「重篤な腎機能障害のある患者」の項目に下記が追記されました。
なお、低カルシウム血症の副作用については従来から重大な副作用の項目に記載されています。
国内の医療情報データベースを用いた疫学調査において、骨粗鬆症の治療にビスホスホネート系薬剤を使用した腎機能障害患者のうち、特に、高度な腎機能障害患者(eGFRが30mL/min/1.73m2未満)で、腎機能が正常の患者と比較して低カルシウム血症(補正血清カルシウム値が8mg/dL未満)のリスクが増加したとの報告がある。
⑥グリベック(イマチニブ)【重大な副作用】
重大な副作用に「天疱瘡」が追加となりました。
<重大な副作用>
水疱、びらん、痂皮等が認められた場合には、皮膚科医と相談すること。
⑦アリセプト【用法及び用量】
「レビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制」の効能について、再審査の結果で主要評価項目においてプラセボと本剤群で有意差がでなかったことから、用法及び用量に下記の注意が追記されました。
なお、レビー小体型認知症の認知症症状に対する本剤の有効性については、全てが否定されるものではなく、承認時の臨床試験も併せて考えれば、有効性が期待できる患者も存在するとの判断がされているようです。
投与開始12週間後までを目安に、認知機能検査、患者及び家族・介護者から自他覚症状の聴取等による有効性評価を行い、認知機能、精神症状・行動障害、日常生活動作等を総合的に評価してベネフィットがリスクを上回ると判断できない場合は、投与を中止すること。
投与開始12週間後までの有効性評価の結果に基づき投与継続を判断した場合であっても、定期的に有効性評価を行い、投与継続の可否を判断すること。
⑧アジョビ皮下注オートインジェクター
オートインジェクターの剤形で「4 週間に 1 回 225mg」 を投与する場合にのみ自己注射が可能となりました。そのため、今後は調剤薬局に処方が来る可能性があるため認識しておいたほうがよいかと思います。
なお、「アジョビ皮下注 225mg シリンジ」については在宅自己投与の対象外です。
また、CGRP関連薬剤としてはエムガルティ皮下注、アイモビーグ皮下注がすでに自己注射が可能となっています。
⑨フォシーガ(ダパグリフロジン)
慢性心不全の効能において従来「左室駆出率の低下した慢性心不全患者に投与すること」という記載がされていましたが、左室駆出率が保たれた慢性心不全患者を対象とした臨床試験が完了したことから、この記載が削除され緩和されました。
⑩フェロミア(クエン酸第一鉄ナトリウム)【その他の注意】
従来よりその他の注意に記載されていた歯の着色についての記載に「舌」も追記されました。歯と同様、舌の着色も報告症例が集積されていることが理由です。
<その他の注意>
本剤の投与により歯又は舌が一時的に着色(茶褐色等)することがある。その場合には、重曹等で除去する。















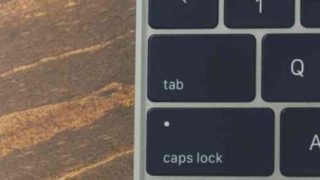




コメント