
2024年夏〜冬の新薬承認情報+効能追加情報のなかから薬局薬剤師に関係がある薬剤の概要をまとめました。
国内3剤目のオレキシン受容体拮抗薬クービビック、「月経困難症」を効能とするアリッサ配合錠、「高カリウム血症」を効能とするビルタサ懸濁用散分包などは処方される可能性があるので把握しておいたほうがよいかと思います。
- ①クービビック錠25mg/50mg(ダリドレキサント)
- ②ユバンシ配合錠(マシテンタン/タダラフィル)
- ③アリッサ配合錠(エステトロール水和物/ドロスピレノン)
- ④ビルタサ懸濁用散分包8.4 g(パチロマーソルビテクスカルシウム)
- ⑤ケサンラ点滴静注液(ドナネマブ)
- ⑥ルプキネスカプセル7.9mg(ボクロスポリン)
- ⑦リジュセアミニ点眼液(アトロピン)
- ⑧ゼップバウンド皮下注アテオス(チルゼパチド)
- ⑨ゼポジアカプセル0.92mg/スターターパック(オザニモド)
- ⑩アジルバ錠、顆粒(アジルサルタン)【効能追加】
- ⑪プレベナー20水性懸濁注(沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン)【効能追加】
- ⑫ツルバダ(エムトリシタビン/テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩)【効能追加】
- ⑬レキサルティ【効能追加】
- ⑭ウプトラビ錠(セレキシパグ)【効能追加】
①クービビック錠25mg/50mg(ダリドレキサント)
「不眠症」を効能とする国内3剤目のオレキシン受容体拮抗薬です。
濁点が多いので薬品名が覚えにくいのですが、QUEST(探求)+VIVA(生き生きとした)+IQ [intelligence](特性・叡智)から命名されています。
ベルソムラ同様にクラリスロマイシンなどの薬剤が禁忌であり、デエビゴ同様に中程度のCYP3A阻害剤と併用する場合は、低規格の用量(25mg)となるので注意が必要です。(ベルソムラの場合は10mgへの減量を「考慮」という記載なので減量は必須ではありません)
<用法及び用量>
通常、成人にはダリドレキサントとして1日1回50mgを就寝直前に経口投与する。なお、患者の状態に応じて1日1回25mgを投与することができる。
<用法及び用量に関連する注意>
中程度のCYP3A阻害剤と併用する場合は、本剤の血漿中濃度が上昇し、傾眠等の副作用が増強するおそれがあるため、患者の状態を慎重に観察した上で、本剤投与の可否を判断すること。
なお、投与する場合は、1日1回25mgとし、慎重に投与すること。
また、これもデエビゴに似てますが重度の肝機能障害(Child-Pugh分類C)のある患者は禁忌、中等度の肝機能障害(Child-Pugh分類B)を有する患者は低規格の用量(25mg)となるので肝硬変患者などでは注意が必要です。
なお、Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類は肝性脳症、腹水、血清総ビリルビン値、血清アルブミン、プロトロンビン時間の5項目の重症度を点数化し合計点数から肝臓の障害度をA〜Cに分類して評価します。
検査値から分かる血清ビリルビン、血清アルブミン、プロトロンビン時間の以外にも腹水や肝性脳症などの重症度も用いるので検査値を見せてもらったとしても薬局側で判別することは難しいです。
一応、血清ビリルビン、血清アルブミン、プロトロンビン時間の値が全て軽症に分類されれば残りが重症だったとしてもCには点数が届かないのでCではないと判断することはできますが、クービビックのように代替薬がある場合は素直に肝硬変の程度によっては禁忌となることを話して疑義照会しベルソムラなどの薬剤に変更を検討するのがよいかと思います。
②ユバンシ配合錠(マシテンタン/タダラフィル)
「肺動脈性肺高血圧症」を効能とするエンドセリン受容体拮抗薬マシテンタン10mgとPDE5阻害薬タダラフィル40mgを含有した配合製剤(オプスミット+アドシルカ)です。
第一選択薬とはせずに、原則としてマシテンタン10mg1日1回およびタダラフィル40mg1日1回の併用治療を受けている場合に同薬の使用を検討することとされています。
「Yu」は「you」(個別化)、「VANCI」は「moving forward/advancing in life.」(人生において前進する・進歩するさま)から命名されています。
③アリッサ配合錠(エステトロール水和物/ドロスピレノン)
「月経困難症」を効能とする日本初のエステトロール(E4)を含有する低用量エストロゲン・プロゲスチン(LEP)配合薬です。
既存のLEP配合薬のエチニルエストラジオール(EE)に比べてE4は、血管および肝臓のエストロゲン受容体などへの作用が少なく、子宮・卵巣に選択的に作用することで静脈血栓塞栓症の低減が期待されています。
同薬は、実薬錠(ピンク色)24錠と、プラセボ錠(白色~微黄白色)4錠からなる28錠がPTPシートに包装されています。
Alyssum の花を語源とし、花言葉の“美しさを超えた価値”“飛躍”に由来するほか、女性名をイメージした名称となっているようです。
<用法及び用量>
1日1錠を毎日一定の時刻に定められた順に従って(ピンク色錠から開始する)28日間連続経口投与する。
以上28日間を投与1周期とし、出血が終わっているか続いているかにかかわらず、29日目から次の周期の錠剤を投与し、以後同様に繰り返す。
④ビルタサ懸濁用散分包8.4 g(パチロマーソルビテクスカルシウム)
「高カリウム血症」を効能とする陰イオンポリマーとカルシウム-ソルビトールの対イオンで構成される非吸収性の陽イオン吸着ポリマーです。
本剤はナトリウムを含まないため、浮腫等の体液負荷を高める副作用が理論上想定されず、食塩制限などにより体液管理を含め疾患管理が推奨されている慢性腎臓病や心不全を併存する高カリウム血症患者にとって、有用な治療選択肢になることが期待されています。
<用法及び用量>
通常、成人には、パチロマーとして8.4gを開始用量とし、水で懸濁して、1日1回経口投与する。以後、血清カリウム値や患者の状態に応じて適宜増減するが、最高用量は1日1回25.2gとする。
類薬のロケルマ懸濁用散分包との違い
類薬であるロケルマ懸濁用散分包との大きな違いは下記です。
①2回かき混ぜる必要がある。
コップ等に規定の量の水を注いだ後、ビルタサ を入れてよくかき混ぜ、その後さらに残りの水を追加して再度かき混ぜて服用するため2回かき混ぜる必要があります。(ロケルマは1回)
(参考)
ビルタサ懸濁用散分包を服用される方へ
②腸管穿孔、腸閉塞についての注意
腸管穿孔、腸閉塞を起こす可能性が否定できないため、便秘に引き続き持続する腹痛、嘔吐等の症状があらわれた場合には、医師等に相談するように指導する必要があります。
これは国内及び海外臨床試験においては腸管穿孔や腸閉塞の発現は認められませんでしたが、類薬であるポリスチレンスルホン酸ナトリウムなどで報告があるため設定されています。
③冷蔵庫で保管
2 ~ 8 ℃で保存のため、薬局では冷蔵庫に保管する必要があります。
患者が保管する場合は室温(1〜30℃)で保管することも可能ですが、その場合3ヵ月以内に使用する必要があります。
⑤ケサンラ点滴静注液(ドナネマブ)
「アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制」を効能とし、アミロイドβプラークを標的とする早期AD治療薬(ヒト化抗N3pGアミロイドβ)モノクローナル抗体製剤)です。
既存薬のレケンビ点滴静注は2週間に1回投与ですが、ケサンラは4週間に1回投与であり来院間隔を減らすことができます。
点滴製剤のため薬局で調剤することはありませんが、レケンビ同様に抗血栓薬が併用注意であり、「抗血栓薬による治療が必要な場合は、本カードの医療機関連絡先までご連絡ください。」といった旨が記載されたカードが存在します。
そのため、「ケサンラを使用中に他院で抗血栓薬などが追加となるような処方の際」には患者がカードをもらっているか、もらっている場合は抗血栓の処方医にもちゃんと見せたかなどを確認する必要があります。
また、特にケサンラ処方病院から治療カードなどの注意喚起をされていない場合でも、抗血栓薬処方時に患者がケサンラの併用を抗血栓薬の処方医に伝えていない場合は情報伝達の意味合いで連絡をしたほうがよいかもしれません。薬局側からケサンラ処方医に抗血栓薬治療が開始されたことを情報提供することも検討されます。
⑥ルプキネスカプセル7.9mg(ボクロスポリン)
「ループス腎炎」を効能とするカルシニューリン阻害薬です。
lupusを表す「Lup」と腎臓の薬である「K」、親切という意味の「Kindness」から命名されています。
カルシニューリンン阻害薬というと併用禁忌に注意が必要なイメージがありますが、「シクロスポリンで禁忌であるロスバスタチン、ピタバスタチン」、「タクロリムスで併用禁忌であるカリウム保持性利尿薬」などは併用注意であり、一方でクラリスロマイシンなどの「強いCYP3A4阻害作用を有する薬剤」は併用禁忌となっています。
⑦リジュセアミニ点眼液(アトロピン)
日本初の「近視の進行抑制」を効能とするアトロピン製剤です。
投与対象は基本的には小児で1日1回就寝前に点眼します。
なお、本剤は薬価基準未収載医薬品として販売予定のため、保険対象外となります。
⑧ゼップバウンド皮下注アテオス(チルゼパチド)
マンジャロ皮下注アテオスと同成分の「肥満症」を効能とする週1回皮下投与の製剤です。規格が6つあり、過誤にも注意が必要です。
チルゼパチドを含有しているため、マンジャロ等他のチルゼパチド含有製剤あるいはその他のGLP-1受容体作動薬等のGLP-1受容体に対するアゴニスト作用を有する薬剤と併用しないこととされています。
最適使用推進ガイドライン対象品目であるため、気軽に処方できる薬剤ではありません。
なお、類薬としてはすでに2024年2月にセマグルチド製剤のウゴービ皮下注 SDが発売されています。
<効能又は効果>
肥満症
ただし、高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動療法を行っても十分な効果が得られず、以下に該当する場合に限る。・BMIが27 kg/m2以上であり、2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する
・BMIが35 kg/m2以上<用法及び用量>
通常、成人には、チルゼパチドとして週1回2.5mgから開始し、4週間の間隔で2.5mgずつ増量し、週1回10mgを皮下注射する。なお、患者の状態に応じて適宜増減するが、週1回5mgまで減量、又は4週間以上の間隔で2.5mgずつ週1回15mgまで増量できる。
⑨ゼポジアカプセル0.92mg/スターターパック(オザニモド)
「中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る)」を効能とするスフィンゴシン1-リン酸(S1P)受容体調節剤です。
心拍数の低下等がみられることがあるため、漸増する用法・用量になっており1~7日目はスターターパック、8日目以降は0.92mgカプセルを使用します。
心拍数低下による、失神、浮動性めまい、息切れなどの症状以外にも眼科領域の注意として黄斑浮腫についても注意喚起されており、投与中は眼底検査を含む定期的な眼科学的検査が必要とされています。
<用法及び用量>
通常、成人にはオザニモドとして1~4日目は0.23mg、5~7日目は0.46mg、8日目以降は0.92mgを1日1回経口投与する。
また、飲み忘れ、受診遅れなどで一定の休薬期間があった場合は「0.23mgから投与を再開し、用法・用量のとおり漸増すること」というように初期用量からのやり直しとなってしまいます。
特に投与開始後14日以内では1日でも休薬があるとこれに該当してしまうので注意が必要です。
<用法及び用量に関連する注意>
本剤の休薬期間が以下に該当する場合は、休薬前と同一の用量で投与再開した場合に一過性の心拍数低下が生じる可能性があるため、0.23mgから投与を再開し、用法・用量のとおり漸増すること。
・投与開始後14日以内に1日以上の休薬
・投与開始後15~28日の間に7日間を超えて連続して休薬
・投与開始後28日を経過した後に14日間を超えて連続して休薬
⑩アジルバ錠、顆粒(アジルサルタン)【効能追加】
「高血圧症」の効能において、2歳以上6歳未満の小児用量が追加となりました。
なお、6歳以上の小児については以前から記載されています。
⑪プレベナー20水性懸濁注(沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン)【効能追加】
2024年の3月承認時の小児の効能に加えて、発売前に「高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者」に対しての効能も追加となり8月に発売開始となりました。
プレベナー20は従来のプレベナー13に含まれる13の血清型に加え、8、10A、11A、12F、15B、22F及び33Fが含まれる沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンです。従来のプレベナー13は販売終了となります。
なお、小児についてはプレベナー20は10月1日より定期接種が開始となっています。
⑫ツルバダ(エムトリシタビン/テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩)【効能追加】
公知申請にもとづき「HIV-1感染症の曝露前予防」(Pre-Exposure Prophylaxis[PrEP(プレップ)])の効能が追加となりました。HIV曝露前予防薬の効能として承認されるのは国内初となります。なお、この予防としての使用の場合は保険外となります。
PrEPとは、⾮HIV感染者が性交渉などHIV感染リスクがある⾏為の前に抗HIV薬を内服し、HIV感染のリスクを低減する感染予防⽅法で、処⽅通りにPrEPを利⽤することで、性交渉によるHIV感染リスクが約99%低下可能とされています。
PrEPの内服⽅法には、「毎日1錠服用するデイリーPrEP」と「HIV 曝露リスク行為の前後に服用するオンデマンドPrEP」の2種類がありますが、デイリーPrEPのみ効能として承認されました。
ちなみに「暴露後予防(Post-Expousure Prohhylaxis)」のことはPEP(ペップ)と呼ばれ文字が似ているので混同しないように注意が必要です。
⑬レキサルティ【効能追加】
「アルツハイマー型認知症に伴う焦燥感、易刺激性、興奮に起因する、過活動又は攻撃的言動」の効能が追加となりました。
もともとの「統合失調症」の効能、近年効能追加となった「うつ病・うつ状態」の効能に加えてこれで3つの効能を有することになりますが、それぞれ用法・用量が異なるのでかなり複雑な添付文書となっています。
また、「用法及び用量に関連する注意」に記載されているCYP3A4阻害やCYP2D6 阻害剤との併用時のレキサルティの用量制限についても効能ごとに異なっており、非常に複雑になっています。
阻害薬が処方された際にすでに制限用量を超える用量でレキサルティを服用中している場合は実質的には、これらのCYP2D6阻害剤やCYP3A4阻害剤の使用ができなくなります。
実際にこのような併用処方がでた場合には疑義照会して阻害薬側を変更する対応が妥当ですが、代替が難しい場合はレキサルティを記載の用量に減量するかを疑義照会する対応となるかと思います。
中等度以上のCYP3A、CYP2D6阻害剤とはなにか
中程度以上の阻害薬とは具体的にどの薬剤が該当するかは添付文書には一部しか記載がないため不十分ですが、阻害作用を有する代表的な薬剤については製薬会社のサイト内の「適正使用に関する情報」の下のほうに掲載されている「CYP2D6阻害剤、CYP3A阻害剤の一覧」に記載されています。
レキサルティにかかわらず、中等度以上のCYP2D6阻害剤、CYP3A阻害剤は薬剤師として把握しておく必要があるので目を通しておくことを強くお勧めします。
(参考) レキサルティ錠1mg、2mg 適正使用に関する情報 (大塚製薬医療関係者向け情報サイト)https://www.otsuka-elibrary.jp/product/di/rx1/tekisei/index.html
⑭ウプトラビ錠(セレキシパグ)【効能追加】
小児の効能が追加となりました。また、これに伴いウプトラビ錠小児用0.05 mgの規格が追加されました。







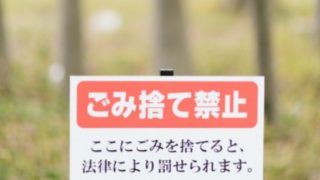












コメント